【SFA】ミラクル・クエスチョンでカウンセリングの流れを変えてみた話

ミラクル・クエスチョンとは?
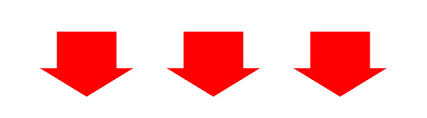
カウンセリングの行き詰まりを変えた体験
ミラクル・クエスチョンは絶望の状態から生まれた
シンプル・ミラクルの使い方
奇跡は問題が解決できてなくても起こせる
参考文献
![解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き 解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ii-lO9MVL._SL160_.jpg)
解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き
- 作者: ピーター・ディヤング,インスー・キム・バーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2016/02/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

解決のための面接技法―ソリューション・フォーカスト・アプローチの手引き
- 作者: ピーターディヤング,インスー・キムバーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2008/08/08
- メディア: 単行本
- クリック: 21回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
SFAについてもっと詳しく知りたい人はこちらもオススメです。
SFAの開発者、インスー・キム・バーグによる、SFAの技法がみっちり詰まった一冊です。
最新の第4版は事例が増えて、とても濃い内容になっています。本はかなりデカイです。もはやこれは図鑑です。本を持ち歩く人はオススメしません。
本を持ち歩くことが多い人は、単行本サイズの第3版がオススメです。
ちなみに、僕は、第4版を持っています。本気なので(笑)。
ぜひ、Amazonでポチってみてくださいね!
赤ちゃんにとって大切なアタッチメントってどんなもの?

こんにちは。どいつよしです。
乳幼児期に愛着の絆を結ぶとどうなるのか?
脳と肉体の健常な成長と発達を促す。↑遺伝子の持っている可能性を最大限に実現するため。良心・同情・共感・愛情のやり取りができるようになる。↑人間関係作りの能力の基礎がしっかりするため。恐怖・不安・怒りを抑え、喜び・快感・興味・楽しむことができるようになる。↑自制・自癒能力が養われるため。
愛着の絆とはどういうものなのか?
保護者と子どもの間に互いに結ぶ特別な、深い、恒久的な、生理的で社会的で情緒的で知的な絆
愛着の絆を結ぶというのは?
母またはその代理となる人が子どもに感じる「可愛い・いとしい・守ろう」という想いと、子どもが母またはその代理人に寄せる慕情と全面的な信頼によって結ばれる
愛着の絆を結ぶ時期はいつ?
0〜生後3ヶ月:愛着形成に大切な時期0歳〜3歳まで:愛着が脳の形成を助ける時期〜5歳まで:愛着の絆を自然に結ぶ最適な時期
心の土台を作る時期にも重なる
愛着の絆作りに欠かせない保護者の行動とは?
安心・安全感を与える行動
赤ちゃんと波長を合わせる行動
愛着の絆作りにもスキンシップを
母親と父親共通
母親
父親
おわりに
アタッチメントとは、生後に結ぶ赤ちゃんと保護者の愛着の絆である。愛着の絆を結ぶことが、赤ちゃんと保護者の双方にとってもメリットがある。愛着の絆を結ぶことが、赤ちゃんの心身の成長発達に大きな影響力をもつ。愛着の絆作りにはスキンシップが欠かせない。愛着の絆は母親だけでなく、父親にも必要である。
あわせて読んでみてくださいね
自己肯定感は人間にとってなくてはならないものだった話

こんにちは。どいつよしです。
ついにアメブロデビューしました!
友人のブログ「自己肯定感とフェルトセンス | 【大阪・梅田】不妊カウンセリングルーム with(ウィズ)」にて
「フォーカシングになくてはならないフェルトセンスってどんなもの? 」を紹介していただきました。
ご自身のカウンセリング現場での体験を踏まえて、自己肯定感とフェルトセンスの関係性という切り口で、僕の書いたことをさらにわかりやすく、深めてくださってます。
ぜひ、僕の記事とあわせてよんでくださいね!
そして、友人のブログを読んで、
そもそも、自己肯定感があるときって、どんなときなんだろうか?
という、興味が湧いてきました。
自己肯定感という言葉は、「わたしは自己肯定感があまりないので、、、」というように、自分の自信のなさをフォローするような時によく出てくるように思います。
でも、551蓬莱のCMのように「自己肯定感があるとき〜!」「ないとき〜!」って、はっきり区別できるようなものでもないように思うんですよね。
551蓬莱CM ある時ない時おかげ様で70年編 2015年
元気ハツラツにオロナミンCをグイッと飲んでいるイメージが、自己肯定感があるときとするならば、元気ハツラツしてない人は、みんな自己肯定感がない人になってしまいます。
自己肯定感というのは、何かを基準にして「ある」とか「ない」とか「高い」とか「低い」とかが決まるものなのか、そうではないものなのか。
今回は、そのあたりをはっきりさせたいと思っていろいろ調べてみたことを、書いていきますね。
自己肯定感について驚愕の事実!
今回は、参考図書に、この本を使わせていただきました。

自己肯定感、持っていますか? あなたの世界をガラリと変える、たったひとつの方法 大和出版
- 作者: 水島広子
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2015/11/06
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
その本によると、自己肯定感について驚愕の事実が判明したのです!
その事実とは!?
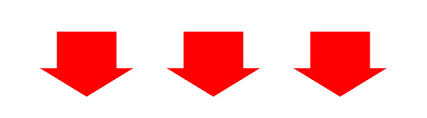
自己肯定感は空気のようなもの〜
なぜ空気のようなものなのか!?
それは、自己肯定感が、
空気のように、
具体的に感じられるものではなく、
普段はその存在を意識しないで過ごしている、
心地よく温かく、自分をぽかぽかと満たしてくれるもの
だから。
空気は、私達が生きていくにはなくてはならないものですが、あまりに当たり前のものなので、その恩恵を感じることがほとんどありません。
しかし、ひとたび空気が足りなくなっているとなると、致命的な問題になり、空気の存在の重要性に気付くことになりますよね。
自己肯定感もそんな感じのものなのだそうです。
当たり前にあるけれど、なくなってくると困る大事なものということですね。
自己肯定感とはどんな気持ち!?
自己肯定感が、空気のようなもので、普段はその存在を意識して過ごしてはいないけれど、私たちにとって大事なものであるということはわかりました。
では、自己肯定感とはどんな気持ちのことなのでしょうか。
水島先生によると、
「自己肯定感」とは、「優れた自分」を誇りに思うことではありません。「ありのままの自分」をこれでよいと思える気持ちです。
とのこと。
自己肯定感=自分を大切にする気持ち
という表現も使われています。
その気持ちがあることで、 ネガティブな思考にとらわれずに、のびのびと温かい人生を歩むことができるのだそうです。
では、どんな状態の時に自己肯定感が「ある」とか「ない」とか「高い」とか「低い」とかになるのでしょうか。
自己肯定感がある(高い)とき〜!
自己肯定感が高い時というのは、自分のダメなところ探しをすることもなく、自分らしい人生を生きていくことができ、自分や身の回りの人や物事、景色を、明るい目でみていくことができるのだそうです。
だから、普段の生活において、少なくとも自分のダメなところ探しをしないで過ごしている時間は、自己肯定感がある状態とか自己肯定感が高い状態ということが言えますね。
そして、そういう時というのは、「今、わたし、自己肯定感ある!」なんて意識することもあまりないですよね。
自己肯定感がない(低い)とき〜!
自己肯定感が低いと、「こんな自分はダメだ」と自己否定的になったり、「こんな自分が、どうやって生きていけるのだろうか」と不安になったり、「何をやってもどうせ意味がない」と無力感を覚えたりするそうです。
また、自己肯定感が低い人は、「自己肯定感が低い」ということについても、自分をネガティブな目で見ているとのこと。
「私は、自己肯定感が低いから、ダメだ」「どうしてこんなに自己肯定感が低いのだろう」というように。
そうなると、自己肯定感が低いということを証明する結果ばかりが目につくようになっていきます。
自己肯定感が低下→自分はダメなやつ→ダメな結果→自己肯定感が低下→自分はダメなやつ→ダメな結果→以後繰り返し
という、無限ループを経ていくことになり、結果として自己肯定感はどんどん下がっていってしまいます。
いつも自分に対して「こんなんじゃダメだ」「どうせできないよ」という評価を下していくことは、自分を傷つけ続けるようなもの。
自分を大切にできないため、結果として、心を病んでしまったり、心身を傷つけるようなことをしたり、絶望感の中、問題行動を起こしたりする場合もあります。
僕の友人も書いてありましたが、カウンセリングに訪れる人や、医療機関で治療に入る人には、自己肯定感がとても低い人が多いのだそうです。
自己肯定感を自分で回復させるには?
自己肯定感は低くなりすぎると、カウンセリングや医療機関にかからないといけなくなる場合がありますが、
心を病んでしまったり、心身を傷つけるようなことをしたり、絶望感の中、問題行動を起こしたりするところまで至っていない場合は、自分で回復させることも可能なようです。
水島先生は、「他人をリスペクトしてみる」という手法をすすめられています。
ここでのリスペクトは、
ありのままの相手に敬意を持ち、尊重する
という意味なのだそうです。
「自分の好きなところ探しをする」ことからではないところが斬新です。
さて、どのようなやり方でおこなっていくのかは、ぜひ、本を手にとってもらえたらと思います。

自己肯定感、持っていますか? あなたの世界をガラリと変える、たったひとつの方法 大和出版
- 作者: 水島広子
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2015/11/06
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
おわりに
いかがでしたでしょうか?
今回は、「フォーカシングになくてはならないフェルトセンスってどんなもの?」が友人のブログに紹介され、自己肯定感とフェルトセンスの関係性について書かれていたことから、僕も自己肯定感をテーマに書いてみました。
今回調べてわかったことは、
自己肯定感は、空気とおなじような、私たちが生きていくにあたって、とても大事なものである。
自己肯定感とは「自分を大事にする気持ち」のことである。
自己肯定感が高いと私たちは自分らしく人生を歩んでいける。
自己肯定感が低くなると、自分を傷つけてどんどん低くなっていくことがあり、健康面や行動面でいろいろな問題が出てくる。
ある・なし・高・低のはっきりとした基準があるわけではない。
自分で回復する手法もある。
ということでした。
個人的には、「空気のようなもの」ということを知ることができたことが一番の収穫でした。
また、自己肯定感が低い人がどんどん低くなっていくプロセスは、僕自身もはまってしまった経験があるので、その苦しさを思い出して、胸が痛くなりました。
仕事などで失敗を怖れるあまり、つい「僕は自己肯定感が低いので」を口にしてしまうことがあるので、気をつけたいと思います。
あと、水島先生は、自分で自己肯定感を回復していく手法として、「他人をリスペクトする」を提案されていますが、
僕は、SFAの例外探しの手法を使った、【「自己肯定感がない」と思わない時がどんな時かを探して、そこを長くしていくようにする】、というのも役に立つのではないかと思います。
最後に、僕のブログを紹介してくださり、自己肯定感について興味を持つきっかけもくださった「自己肯定感とフェルトセンス | 【大阪・梅田】不妊カウンセリングルーム with(ウィズ)」の ほりたたかこ さん。
ほんとうに、ありがとうございました!
あわせて読んでみてくださいね
『ヨチヨチ父』はこれから父親になる人、なったばかりの人に読んでもらいたい本

です。
・あかちゃんとの関わり方・母親となった奥さんとの関わり方・育児における立ち位置や心構え・知っておくと役に立つ“育児あるある”・知っておくと役に立つ“トラブル解消法”

あわせて読んでみてくださいね
フォーカシングになくてはならないフェルトセンスってどんなもの?

フェルトセンスの生い立ち
フェルトセンスってどんなもの?
私たちは常にフェルトセンスとともにある
フェルトセンスは知恵の源泉
フェルトセンスに気づくのは難しい
おわりに
参考文献

- 作者: アン・ワイザーコーネル,Ann Weiser Cornell,大沢美枝子,日笠摩子
- 出版社/メーカー: コスモスライブラリー
- 発売日: 1999/09/01
- メディア: 単行本
- 購入: 6人 クリック: 19回
- この商品を含むブログ (13件) を見る
誰もがフォーカシングをできるようになるための方法がわかりやすく書かれている教示法の本です。
産業カウンセラー仲間には、この本でフォーカシングを体験し、カウンセリングに役立てられるようになったという人もいます。
自分でフォーカシングができるようになりたい人にオススメです。

傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本
- 作者: 池見陽
- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版
- 発売日: 2016/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
ジェンドリンのフォーカシングについてはもちろんのこと、ロジャーズの理論についての誤解を解く内容が書かれていたり、来談者中心療法以外の療法についても、池見先生が解説をされています。
ロジャーズをきちんと理解した上で、ジェンドリンを知ることができる、一石二鳥以上のお得な本でもあります。
ジェンドリンのフォーカシングの方法と、仏教の瞑想の知恵を統合した、「マインドフル・フォーカシング」についての本。フォーカシングとマインドフルネスのそれぞれの理論について学べます。
マインドフルネスの考え方を応用した、フェルトセンスに気付きやすくする準備の方法「GAPの3ステップ」を習得すると、ひとりでもフォーカシングができやすくなりそうです。
ただ、フォーカシングの入門書としては少々難しい内容になっています。
合わせて読んでみてください
父親のスキンシップは母親とは違う効果がある!?

こんにちは。どいつよしです。
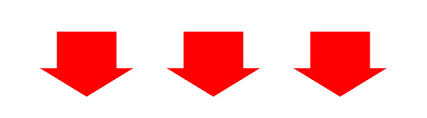
父親と母親のスキンシップの効果の違いとは
父親にオススメのスキンシップ
オキシトシンが出るのも父親と母親で違う
おわりに
あと、勘違いしてほしくないのは、オキシトシンが出るからスキンシップをとるのではないということです。
参考文献

幸せになる脳はだっこで育つ。-強いやさしい賢い子にするスキンシップの魔法-
- 作者: 山口創
- 出版社/メーカー: 廣済堂出版
- 発売日: 2013/11/23
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
僕の乳児院時代のバイブルといえる本のひとつです。抱っこをはじめとするスキンシップの重要性をデータをもとに伝えてくれます。
フォーカシングをしている状態について話し方と視線解析から考えてみた

フォーカシングしている状態はどう見える?
「自分の内側にある言葉やイメージにならない[感じ]に注意を向けていき、その感じに触れながら、それを言葉や文章、動作やイメージなどで表現して[感じ]に秘められた意味を明らかにしようとするプロセス」
フォーカシングをしている状態の話し方
フォーカシングをしている状態の視線


おわりに
参考文献

- 作者: アン・ワイザーコーネル,Ann Weiser Cornell,大沢美枝子,日笠摩子
- 出版社/メーカー: コスモスライブラリー
- 発売日: 1999/09/01
- メディア: 単行本
- 購入: 6人 クリック: 19回
- この商品を含むブログ (13件) を見る
誰もがフォーカシングをできるようになるための方法がわかりやすく書かれている教示法の本です。
産業カウンセラー仲間には、この本でフォーカシングを体験し、カウンセリングに役立てられるようになったという人もいます。
自分でフォーカシングができるようになりたい人にオススメです。

こころの天気を感じてごらん―子どもと親と先生に贈るフォーカシングと「甘え」の本
- 作者: 土江正司,ますいゆうこ
- 出版社/メーカー: コスモスライブラリー
- 発売日: 2008/10/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る
気持ちやからだの感じを天気で表現することで、自分の気持ちや感情をじょうずに相手に伝える力を養うことを目的とした「こころの天気」を使って、教育現場でフォーカシングを活用できるようになる本です。
フォーカシングを知らない人でもすぐに実践しやすいように書かれてあります。
また、後半部分は、子どもの成長・発達と甘えの関連性について書かれており、子育て支援や家庭支援にも役に立つ内容になっています。

傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本
- 作者: 池見陽
- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版
- 発売日: 2016/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
ジェンドリンのフォーカシングについてはもちろんのこと、ロジャーズの理論についての誤解を解く内容が書かれていたり、来談者中心療法以外の療法についても、池見先生が解説をされています。
ロジャーズをきちんと理解した上で、ジェンドリンを知ることができる、一石二鳥以上のお得な本でもあります。
アドラー心理学「嫌われる勇気」は、嫌われる(かもしれない)恐怖にあらがうこと!?

「嫌われる勇気」の誤解を解く!
青年「先生は、わたしに【他者から嫌われろ】と?哲人「嫌われることを恐れるな、といっているのです。」青年「しかしそれは・・・。」哲人「わざわざ嫌われるような生き方をしろとか、悪行を働けといっているのではありません。そこは誤解しないでください。」
「嫌われる勇気」を正しく理解してみる!
嫌われる勇気が必要な人はどんな人?
- 他者からどう思われているかを気にすることにより、何らかの悩みや問題を抱えている人
- 絶えず人に合わせて生きていくことに辛くなっている人。
- 自分よりもいつも他者を優先してしまうことに悩んでいる人。
- 自分が望んだ人生の選択をしてこれなかったと思っている人。
- 自分の立ち位置がわからなくなって困っている人。
- 自意識が過剰なために外へ出ることへのストレスが大きい人
対人関係の悩みや問題の黒幕は本能にあり!
悩みや問題が軽くなった状態とは?
「嫌われる勇気」の正しい意味とは?
嫌われる勇気を持つには?
「どんなに自分が努力をしても10人いて何をしても好きでいてくれるのはせいぜい2人程度。1人は何をしても嫌われる。残りの7人はその時その時で態度を変える。どんなに頑張ってもどうしようもない部分があることに、エネルギーを費やすくらいなら、何をしても好いてくれる2人と仲良くして、あとは自分のためにエネルギーを使ったほうがよい。」
少しずつ自分でデザインする生き方へ変えていく
「課題の分離」をしながら、少しずつ他者との関わり方を変えていくようにすると、嫌われる(かもしれない)恐怖を大きく感じることなく、自分の人生をデザインしていけるようになるのではないかと考えます。
そういう場合には、できるところまでを繰り返して慣れながら、徐々にできる範囲を広げていく、認知行動療法の考え方が役に立ちそうです。
また、「課題の分離」はできるようになったけれど、それをどう言葉で伝えたらいいのかわからないという場合には、相手を傷つけずに自分の主張を伝えるアサーション・トレーニングの手法を取り入れることも、役に立つのではないかと思います。
おわりに
参考文献
アドラー心理学の哲人と、人生を変えたくて相談に訪れた若者の対話形式で書かれているというのが、他の心理学の本にはない新しさがあります。
もし、『嫌われる勇気』の書き方が合わないという人は、こちらをどうぞ。
書かれているアドラー心理学の考え方は同じですが、対話形式ではない、一般的な新書の書き方で書かれていますので、こちらの方が理解しやすいかもしれません。
僕もこちらから先に読みました。

アドラー心理学入門―よりよい人間関係のために (ベスト新書)
- 作者: 岸見一郎
- 出版社/メーカー: ベストセラーズ
- 発売日: 1999/09/01
- メディア: 新書
- 購入: 12人 クリック: 100回
- この商品を含むブログ (31件) を見る
赤ちゃんに慣れるスキンシップ「ちょい撫で」のススメ

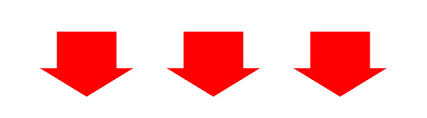
ちょい撫でとは?
ちょい撫での流れの例
ちょい撫では安心してできる状況で
ちょい撫ではほんとにちょいとした時間でもできる
参考文献

幸せになる脳はだっこで育つ。-強いやさしい賢い子にするスキンシップの魔法-
- 作者: 山口創
- 出版社/メーカー: 廣済堂出版
- 発売日: 2013/11/23
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
僕の乳児院時代のバイブルといえる本のひとつです。抱っこをはじめとするスキンシップの重要性をデータをもとに伝えてくれます。
精神の統一と安定を図る呼吸法「数息観」を教わってきた

数息観とは?
数息観の方法
姿勢を作ります。



また、仕事中などで睡魔に襲われた時になんとか目を開けようとして白目を剥いている人っていますよね。極端に言うとあれに近い感じです。笑
呼吸をしていきます。
アンカリングで強化する
良いこと尽くしの呼吸法を日常に取り入れよう!
赤ちゃんには抱っこが必要だとわかる有名な心理学者の研究とは?

こんにちは。どいつよしです。
ワトソンの触れない子育て
ハーロウのサルの愛着実験
おわりに
参考文献

幸せになる脳はだっこで育つ。-強いやさしい賢い子にするスキンシップの魔法-
- 作者: 山口創
- 出版社/メーカー: 廣済堂出版
- 発売日: 2013/11/23
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
僕の乳児院時代のバイブルといえる本のひとつです。抱っこをはじめとするスキンシップの重要性をデータをもとに伝えてくれます。
フォーカシングってなに?どんな生い立ちでどんな効果があるの?

フォーカシングとは?
「自分の内側にある言葉やイメージにならない[感じ]に注意を向けていき、その[感じ]に触れながら、それを言葉やイメージなどで表現して、[感じ]に秘められた意味を明らかにしようとするプロセス」を誰でもできるようにする方法。
「やさしい思いやりをもって先入観なしに自分の<からだ>に耳を傾けるもの」by アン・ワイザー・コーネル
「静かに、心に感じられた「実感」に触れ、そこから意味を見いだす方法」by 日本フォーカシング協会HP
フォーカシングの生い立ち
フォーカシングの効果
・自分がどう感じているか何が欲しいかをもっとわかるようになりたい時に、納得できる答えを自分で導き出すことができるようになる。・押さえきれないくらいのネガティブな感情に巻き込まれそうな時、適度な距離を保って付き合えるようになる。・「できない病」とか「やめられない病」といった行き詰まり状態を解消できる。・自己批判などの自分自身に対する否定的な思いを緩和できるようになる。・自分の心を整理したり、軽くしたりできるようになる。・自分が納得のできる正しい選択をできるようになる。・ストレス性の身体症状を自分で緩和できるようになる。・トラウマに対してやさしく触れることができるようになり、自分で癒せるようになる。
フォーカシングを学んでよかったこと
・自分自身がネガティブな感情にガッツリ巻き込まれる前に、「僕の心の中にネガティブな感情がある」と気付いて、適度な距離をおけるようになったこと。・クライエントの話を追体験できるようになって、伝え返しのクオリティがあがったこと。(追体験はまた改めてブログで書きます)・クライエントの話の内容以外の非言語の部分にも注意して話を聴けるようになったこと。
です。
学びは続くよどこまでも
参考文献

- 作者: アン・ワイザーコーネル,Ann Weiser Cornell,大沢美枝子,日笠摩子
- 出版社/メーカー: コスモスライブラリー
- 発売日: 1999/09/01
- メディア: 単行本
- 購入: 6人 クリック: 19回
- この商品を含むブログ (13件) を見る
誰もがフォーカシングをできるようになるための方法がわかりやすく書かれている教示法の本です。
産業カウンセラー仲間には、この本でフォーカシングを体験し、カウンセリングに役立てられるようになったという人もいます。
自分でフォーカシングができるようになりたい人にオススメです。

こころの天気を感じてごらん―子どもと親と先生に贈るフォーカシングと「甘え」の本
- 作者: 土江正司,ますいゆうこ
- 出版社/メーカー: コスモスライブラリー
- 発売日: 2008/10/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る
気持ちや<からだ>の感じを天気で表現することで、自分の気持ちや感情をじょうずに相手に伝える力を養うことを目的とした「こころの天気」を使って、教育現場でフォーカシングを活用できるようになる本です。
フォーカシングを知らない人でもすぐに実践しやすいように書かれてあります。
また、後半部分は、子どもの成長・発達と甘えの関連性について書かれており、子育て支援や家庭支援にも役に立つ内容になっています。

傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本
- 作者: 池見陽
- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版
- 発売日: 2016/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
ジェンドリンのフォーカシングについてはもちろんのこと、ロジャーズの理論についての誤解を解く内容が書かれていたり、来談者中心療法以外の療法についても、池見先生が解説をされています。
ロジャーズをきちんと理解した上で、ジェンドリンを知ることができる、一石二鳥以上のお得な本でもあります。
ココロの皮むきブログの今後の展開について

こんにちは。どいつよしです。
今日は大安+一粒万倍日という、何かを始めるにはとても縁起の良い日だということなので、このブログの今後の展開でも書いてみようと思います。
まず、心理学の勉強について。
ここのところ、ソリューション・フォーカスト・アプローチ(以下SFAと記載)に関する記事が多くなっていますが、それ以外に学んだ分野のものも書いていくようにしていきます。
フォーカシング、認知行動療法、ゲシュタルト療法、シニア産業カウンセラー講座など、まだまだアウトプットできていないものがあります。
これらの学びをアウトプットすることで、点と点だったものが繋がっていき、僕の中で大きな学びの輪ができると、またワンランク上のレベルでの学びに進めるのではないかと考えています。
また、心理学のたくさんの可能性を、このブログを通して、読んでくださっている人に知っていただけたらという気持ちもあります。
そして新たに、乳幼児の子育てに役立つ情報をお伝えしていくようにします。
僕は、保育や子育ての経験がゼロ、全くのど素人から乳児院に就職しました。それはそれは最初は驚きと戸惑いの日々でしたので、新米パパの気持ちがよくわかります。
TwitterのCM(パパがあかちゃんの泣き止ませ方をTwitterで探すもの)のように右往左往してしまうのもよくわかります。
でも、あのCMのようなやり方は、僕はどちらかというと賛成しかねる部分もあります。
ちゃんとした最低限のことを知っていれば、もっと落ち着いてあかちゃんと過ごせる、あかちゃんと信頼関係を早く築くことができるのになぁと思います。
そこで、僕が驚きと戸惑いの日々の中で学んだたくさんのことから、新しくパパになる人や、育児に興味をもっている男性にとって、役に立つ情報をお伝えしていくことに決めました。
また、僕はアタッチメント・ベビーマッサージ・インストラクターの資格ももっているので、忙しい時でも簡単にできるベビーマッサージやスキンシップを取りながらの遊びについても、あわせて書ければと考えています。
少しでも知識があると育児参加へのハードルが低くなります。そして、男性の育児参加が促されて、女性の負担が軽くなってほしい、育児に行き詰まっての悲しい結末が少しでもなくなってほしい、そういう願いもあります。
それと、実はね、乳幼児の子育てと心理学ってけっこう繋がりがあるんですよ。キャリアコンサルティングにも繋がっていくとも思っています。
だから、乳幼児の育児をアウトプットすることも、僕にとっては心理学の学びを深めることになるんですよね。
・・・ということで、ここまで書いて、かなり風呂敷を広げてしまったなという感じはしますが(^_^;)
ブログにアウトプットしたいことがたくさんあるので、僕の自由に使える時間をいかに有効に活用できるかが勝負になってきますが、できるだけ間隔を開けずに書いていければと思います。
今日書いたことが自分自身への良いプレッシャーになればいいなと思います。
今後とも『ココロの皮むき』ブログをよろしくお願いします。
【SFA】気持ちの程度を知るためにスケーリング・クエスチョンを使ってみたらどうなったか

さて、SFAの技法のひとつに「スケーリング・クエスチョン」というものがあります。少しおさらいをしましょう。
スケーリング・クエスチョンのおさらい
「傷ついた」と繰り返す相談者にスケーリング・クエスチョンを使う
さらに、もっとよい言い回しのスケーリング・クエスチョンがあった!
おわりに
いかがでしたか?
今日は、SFAの技法のひとつであるスケーリング・クエスチョンをクライエントの気持ちの程度を知るために使ってみたことについて書きました。
参考文献
![解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き 解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ii-lO9MVL._SL160_.jpg)
解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き
- 作者: ピーター・ディヤング,インスー・キム・バーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2016/02/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

解決のための面接技法―ソリューション・フォーカスト・アプローチの手引き
- 作者: ピーターディヤング,インスー・キムバーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2008/08/08
- メディア: 単行本
- クリック: 21回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
コンプリメントについて専門的に学んでみたい人、SFAについてもっと詳しく知りたい人はこちらがオススメです。SFAの開発者、インスー・キム・バーグによる、SFAの技法がみっちり詰まった一冊です。
最新の第4版は事例が増えて、とても濃い内容になっています。本はかなりデカイです。もはやこれは図鑑です。本を持ち歩く人はオススメしません。本を持ち歩くことが多い人は、単行本サイズの第3版がオススメです。
ちなみに、僕は、第4版を持っています。本気なので(笑)。
【SFA】コンプリメントはギャンブルで大当たりしたときと同じ脳が活動している!?

「褒める」は脳科学的にも重要である
さて、本題に入りますね。
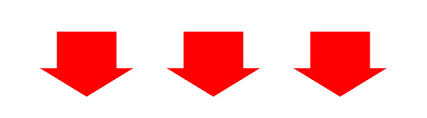
柿木さんによると、褒められるというのは、人間にとって快感の一つとのこと。しかも、その快感は強烈な長期記憶として貯蔵され、忘れることはないのだそうです。
コンプリメントの効果をもっと高めるには?
まとめ
参考文献
この本には、悩むほどでもないことを必要以上に気にせず、悩まずにいられるようになるための、脳の力を活かした31のトレーニングが載っています。
脳の働きをまじえながら解説してくれているので、トレーニング方法に説得力があります。科学的に根拠があるストレス解消法を身につけたい方にもオススメです。
ビジネス心理コンサルティング株式会社の代表取締役をされている林恭弘先生の本。山田洋次監督の褒める姿勢のセピソードはこちらに載ってあります。
また、この本には、人間関係で疲れてしまいがちな人に向けて、疲れるメカニズムと苦手な人間関係から解放され、ラクになる考え方や接し方のコツが紹介されています。
心理学にあまり馴染みがない人にもわかりやすいように、専門用語は少なめに、事例は多めに書かれているという点でもオススメの一冊です。
![解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き 解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ii-lO9MVL._SL160_.jpg)
解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き
- 作者: ピーター・ディヤング,インスー・キム・バーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2016/02/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

解決のための面接技法―ソリューション・フォーカスト・アプローチの手引き
- 作者: ピーターディヤング,インスー・キムバーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2008/08/08
- メディア: 単行本
- クリック: 21回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
コンプリメントについて専門的に学んでみたい人、SFAについてもっと詳しく知りたい人はこちらがオススメです。SFAの開発者、インスー・キム・バーグによる、SFAの技法がみっちり詰まった一冊です。
最新の第4版は事例が増えて、とても濃い内容になっています。本はかなりデカイです。もはやこれは図鑑です。本を持ち歩く人はオススメしません。本を持ち歩くことが多い人は、単行本サイズの第3版がオススメです。
ちなみに、僕は、第4版を持っています。本気なので(笑)。




