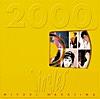【SFA】中島みゆきの『瞬きもせず』は「例外探し」と「コンプリメント」の曲だった!?

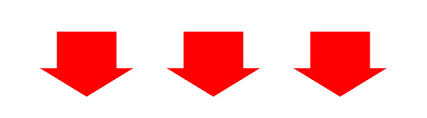
そうなんです、この曲の歌詞には、SFAの「眼の前の人の闇の部分を認めながらも光の部分を見ていこう」という考え方に通じるところが多いんです。
サビの部分がSFA!
君を映す鏡の中 君を誉める歌はなくても僕は誉める 君の知らぬ君についていくつでもあのささやかな人生を良くは言わぬ人もあるだろうあのささやかな人生を無駄となじる人もあるだろうでも僕は誉める 君の知らぬ君についていくつでも
「例外探し」と「コンプリメント」についてのおさらい
君を映す鏡の中 君を誉める歌はなくても僕は誉める 君の知らぬ君についていくつでもあのささやかな人生を良くは言わぬ人もあるだろうあのささやかな人生を無駄となじる人もあるだろうでも僕は誉める 君の知らぬ君についていくつでも
コンプリメントは普段の生活にも使える!
ぜひ、読んでみてくださいね!
終わりに
いかがでしたか?ソリューションフォーカストアプローチっていったいなんなのさ?

あと、僕自身の復習も兼ねて。笑
では、いってみましょー!!
SFAのはじまり
SFAの特長は解決志向であること
- なぜ、こうなったのか
- どこ(誰)がいけなかったのか
- どこを取り除けばいいのか
- どこを治さなくてはいけないのか
- 問題を解決した姿はどんな姿か?
- そこへ向かうために何が必要か?
- どんな行動が必要か?
- 今すでにどんなリソース(資源)を持っているか?
傾聴は基本中の基本
リソースを探すための様々な質問とコンプリメント
例外探しの質問であり、
関係性の質問であり、
スケーリング・クエスチョンであり、
コーピング・クエスチョンであり、
ミラクル・クエスチョンです。
そして、クライエントのできているところを再認識してもらうためのコンプリメント(称賛・ねぎらい)を適時いれていくことで、元気づけをおこなっていきます。
疲れないカンセリングが可能
技法は普段の生活でも使える
おわりに
参考文献
![解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き 解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ii-lO9MVL._SL160_.jpg)
解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き
- 作者: ピーター・ディヤング,インスー・キム・バーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2016/02/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

解決のための面接技法―ソリューション・フォーカスト・アプローチの手引き
- 作者: ピーターディヤング,インスー・キムバーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2008/08/08
- メディア: 単行本
- クリック: 21回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
SFAについてもっと詳しく知りたい人はこちらもオススメです。
SFAの開発者、インスー・キム・バーグによる、SFAの技法がみっちり詰まった一冊です。
最新の第4版は事例が増えて、とても濃い内容になっています。本はかなりデカイです。もはやこれは図鑑です。本を持ち歩く人はオススメしません。
本を持ち歩くことが多い人は、単行本サイズの第3版がオススメです。
ちなみに、僕は、第4版を持っています。本気なので(笑)。
ぜひ、Amazonでポチってみてくださいね!
欠けているところとは、私がネガティブな感情を抱いて勝手にそう思っているところ!?

こんにちは。どいつよしです。
僕はネガティブ感情を抱き、松岡修造はポジティブ感情を抱く
①私に関係する事柄がある②その事柄にネガティブな感情を抱く③欠けているところとして認識する

欠けているところもその人にとって大切なもの
欠けているところも問題を解決する資源(リソース)
・ひどい歯並びに悩み、何度か自殺未遂をしたこともある女性が相談にきました。・エリクソンは彼女の話を聞いて「そのすきっぱで何かできませんか?」と尋ねるのです。・エリクソンは「まだ死ぬの早い、どうせ死のうと考えているのなら、死ぬ前にひとつお願いがあります。」と言って、すきっぱから水を飛ばす技を練習すること、3メートル飛ばせるように的も作って当てるようにすることを提示します。・女性は不信感を持ちつつも、言われたとおり、会社の給湯室で練習をするようになります。・そして、それをたまたまのぞいた男性社員があらわれ、その男性に水をかけてしまいます。・そんなハプニングにめげずに練習を続けていると、今度は男性が水鉄砲で女性の顔を狙ってくるようになります。・そして、お互いの親交が深まり、最終的に結婚しました。
まとめ

あわせて読んでみてください
欠けているところよりできているところを見るためにやってはいけないこととは!?


なぜ欠けているドーナツが気になるの?
欠けているところがどうしても気になってしまう僕
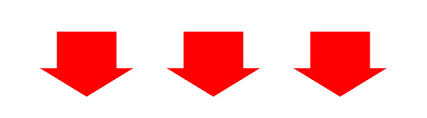
できているところが残っていくようにするためには?
まとめ
参考文献

1日5分 「よい習慣」を無理なく身につける できたことノート
- 作者: 永谷研一
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2016/06/27
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
できていることを見ることを促してくれるコツが書かれてあります。
小さい成功を活用して、成功体験を増やしていくことや、大きい成功を掴むことへつなげていくことも書かれています。
まずは気軽に本に書かれていることを参考にして、「できたこと」をノートに書いていくことから始めてみられてはいかがでしょうか。
カウンセリングを受けてみたいなら
あわせて読んでみてください
普段の人間関係にも使える!コンプリメント(ほめる・ねぎらう)の効果を最大にするためにできることとは?

コンプリメントのおさらい
最高のほめ言葉を伝える達人の話
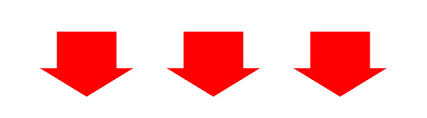
最高のコンプリメントができるようになるには?
・相手のどこがすばらしいのか・相手のどこに自分の心が動かされたのか・どのように自分が関われば、さらにすばらしさを引き出すことができるのか
謙遜の壁を超えていけ!
おわりに
・相手のどこがすばらしいのか・相手のどこに自分の心が動かされたのか・どのように自分が関われば、さらにすばらしさを引き出すことができるのか
参考文献
↑↑ ビジネス心理コンサルティング株式会社の代表取締役をされている林恭弘先生の本。
![解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き 解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ii-lO9MVL._SL160_.jpg)
解決のための面接技法[第4版]―ソリューション・フォーカストアプローチの手引き
- 作者: ピーター・ディヤング,インスー・キム・バーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2016/02/05
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

解決のための面接技法―ソリューション・フォーカスト・アプローチの手引き
- 作者: ピーターディヤング,インスー・キムバーグ,桐田弘江,玉真慎子,住谷祐子
- 出版社/メーカー: 金剛出版
- 発売日: 2008/08/08
- メディア: 単行本
- クリック: 21回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
コンプリメントについて専門的に学んでみたい人、SFAについてもっと詳しく知りたい人はこちらがオススメです。
SFAの開発者、インスー・キム・バーグによる、SFAの技法がみっちり詰まった一冊です。
最新の第4版は事例が増えて、とても濃い内容になっています。本はかなりデカイです。もはやこれは図鑑です。本を持ち歩く人はオススメしません。
本を持ち歩くことが多い人は、単行本サイズの第3版がオススメです。
ちなみに、僕は、第4版を持っています。本気なので(笑)。
ぜひ、Amazonでポチってみてくださいね!
SFAの学びの記録
自分にとって心地よいことをするとココロとカラダが健康になるって知ってますか!?



「人は習慣によってつくられる」とアリストテレスは言葉を残し、「人の違いが生じるのはそれぞれの習慣によってである」と孔子は説いたそうです。多くの先人たちが「人は習慣によって、なりたい自分になれる」と教えてきました。例えば、節制している人は節度のある人になり、笑顔を心がけている人は機嫌のいい人になると。言い換えれば、人は習慣によって、整った暮らしができるようになったり、気分のいい日々を送ったりできるということでもあるのではないでしょうか。心地のよい暮らしをしたければ、毎日何かひとつ、丁寧にやってみるとか、心が整うことをしてみるとか、習慣にしていくことから始めるのがいいかと思うのです・・・。
やっぱり!
なぜ心が健康になるのか?〜心理学の視点より
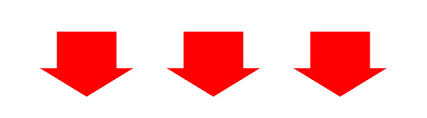
なぜ心が健康になるのか?〜禅の視点より
雑誌を参考に心地よいことをやってみよう
・その日の気分や体調に合わせて調合したハーブティーを持ち歩く・寝る前にスプーン一杯のハチミツを食べる・満月の夜に月の写真を撮る・出かける前に靴を磨く・帰宅前にカフェに寄って日記を書く・・・などなど
![&Premium(アンド プレミアム) 2019年 06月号 [心地よく暮らす人が、習慣にしていること。] &Premium(アンド プレミアム) 2019年 06月号 [心地よく暮らす人が、習慣にしていること。]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/419B0El5HDL._SL160_.jpg)
&Premium(アンド プレミアム) 2019年 06月号 [心地よく暮らす人が、習慣にしていること。]
- 出版社/メーカー: マガジンハウス
- 発売日: 2019/04/20
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る
はじめはつまみ食い程度にやってみる
あわせて読んでほしい記事
『今日が人生最後の日だと思って生きる』は人によっては逆効果になる!?

こんにちは。どいつよしです。
私は17歳のときに「毎日をそれが人生最後の一日だと思って生きれば、その通りになる」という言葉にどこかで出合ったのです。それは印象に残る言葉で、その日を境に33年間、私は毎朝、鏡に映る自分に問いかけるようにしているのです。「もし今日が最後の日だとしても、今からやろうとしていたことをするだろうか」と。「違う」という答えが何日も続くようなら、ちょっと生き方を見直せということです。
自分はまもなく死ぬという認識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら、永遠の希望やプライド、失敗する不安…これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです。本当に大切なことしか残らない。自分は死ぬのだと思い出すことが、敗北する不安にとらわれない最良の方法です。我々はみんな最初から裸です。自分の心に従わない理由はないのです・・・
今日が人生最後の日だと思って生きる効果とは?
・自分の本当にやりたいことが明確になる・時間を有効活用するようになる・自分で限界を決めて諦めることがなくなる・最大の成果が出せるようになる・後悔のない人生を歩めるようになる・気持ちが前向きになる・だらしない生活にサヨナラができる・人に優しくなれる・大切な人に感謝の言葉を言える
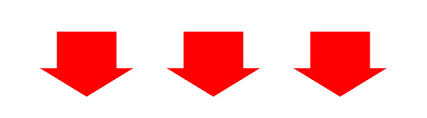
自分に厳しい人にとっては逆効果!?

できたことノートとの出会いとカウンセリング
今日が人生最後の日だなんて思わない!

1日5分 「よい習慣」を無理なく身につける できたことノート
- 作者: 永谷研一
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2016/06/27
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
メンタルヘルスのプロの助けを得ることで、自分ひとりではどうしようもなかった苦しみから解放されるきっかけが得られる思います。
他の人のブログの紹介
ジョブズもやってた「今日が人生最後の日」と仮定したくなる理由と効果 | 知識から意識へ~幸せへの近道~|活学ナビゲーション
あわせて読んでほしい記事
『おしっこちょっぴりもれたろう』には対人関係を良くするヒントが書かれてある!?

こんにちは。どいつよしです。
『おしっこちょっぴりもれたろう』とは!?
↑本当はこんな言い方ではない。↑

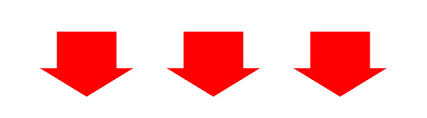

なぜ対人関係を良くするヒントなのか!?
相手の領域に入り込む例え
自分の領域について責任を持たない例え
親子で読んでみるのがオススメ!
おわりに
参考文献
本文中にも書かせて頂いた対人関係療法の水島広子先生の本。
【自分の領域と相手の領域を区別する】を柱にして、いろんな事例が載っていますので、【自分の領域と相手の領域を区別する】を理解するにはもってこいの本です。

誰と会っても疲れない「気づかい」のコツ 対人関係療法のプロが教える
- 作者: 水島広子
- 出版社/メーカー: 日本実業出版社
- 発売日: 2017/09/15
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
あわせて読んでほしい記事
「人間関係」と「対人関係」の違いってわかりますか!?

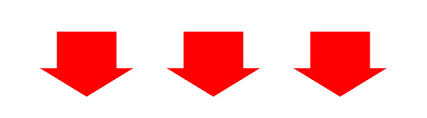
調査結果のご報告
人間関係について

対人関係について

この違いを知って気づいたこと
おわりに
おすすめ記事
【傾聴力アップ】『おしっこちょっぴりもれたろう』には共感的理解を実践するヒントが隠されている!?

こんにちは、どいつよしです。

カウンセリング・マインドをもったなかま
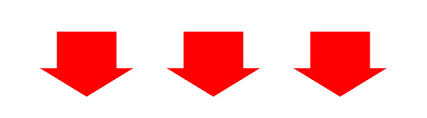
ドーン!!
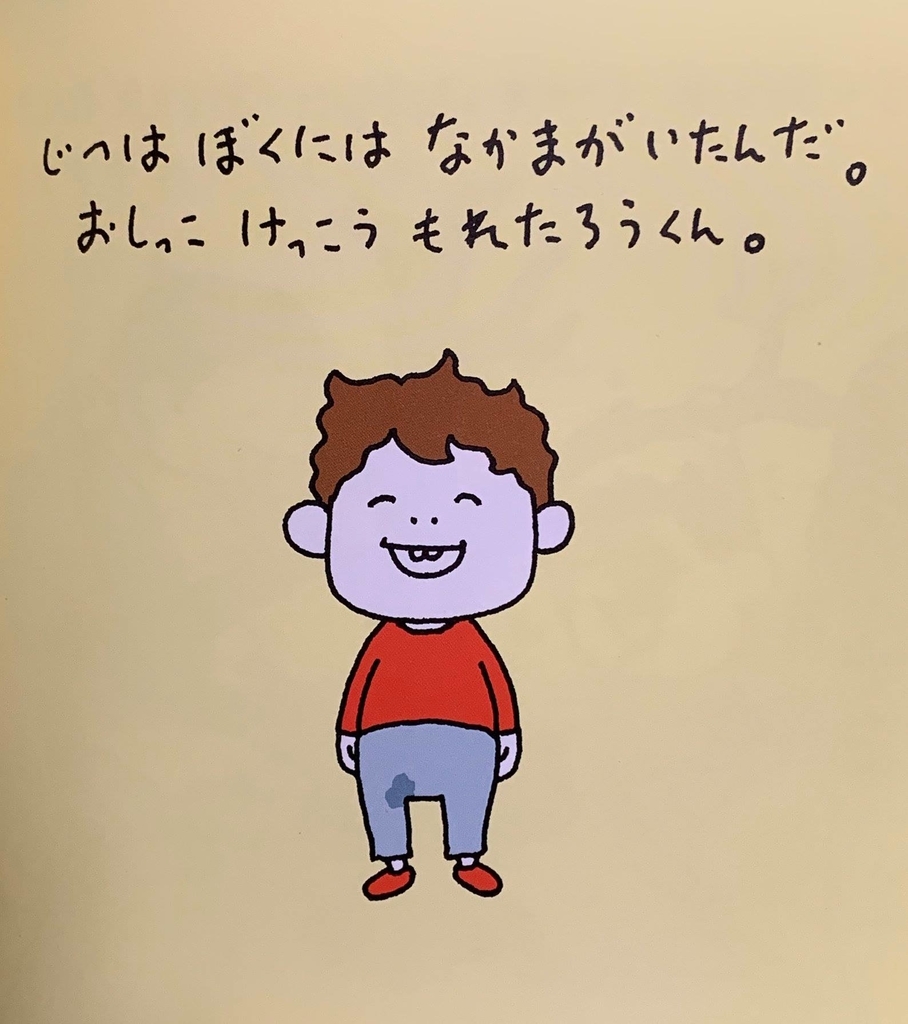
なぜ、きもちをわかってくれたと思えたのか!?
おわりに
Amazonでもちょっぴりもれたろう
あわせてどうぞ
【傾聴力アップ】受容、共感、自己一致は技法ではなく態度だということを知っていますか!?

こんにちは。どいつよしです。
「ロジャーズの3条件」とは?
「ロジャーズの3条件」は実践が難しい!?
「ロジャーズの3条件」は技法ではない!?
講座で池見先生がお話されたのは、「ロジャーズは技法ではなく姿勢や態度を伝えようとした」ということでした。池見先生のお話しにより、僕が追いかけていた、「これが受容だ!」「これが共感だ!」「これが自己一致だ!」という技としての完成形というのは、そもそもそういう技は無いということがわかりました。
一致(自己一致)、無条件の肯定的配慮(受容)、共感的理解(共感)がセラピスト(カウンセラー)の態度条件であり、セラピー関係の構築にとって不可欠な人間的態度であると考えられる
とありました。なんと、テキストにもしっかり【態度】と書いてあるではないですか!
おわりに
池見陽先生の本
このブログの参考文献にもさせて頂いている、2冊を紹介します。
『心のメッセージを聴く』は、ロジャーズの3条件を「カウンセリング・マインド」という表現で説明していて、普段の生活レベルへの活かし方も書かれています。ロジャーズの来談者中心療法についてもたくさん書かれています。
一方で、『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング』はロジャーズの理論についての誤解を解く内容が書かれていたり、来談者中心療法以外の療法についても、池見先生が解説をされています。
そして、その上で、来談者中心療法のアップデート版ともいえる、フォーカシング指向心理療法について、事例を交えて書かれています。
ロジャーズをきちんと理解した上で、ジェンドリンを知ることができる、一石二鳥以上のお得な本でもあります。

傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本
- 作者: 池見陽
- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版
- 発売日: 2016/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
ぜひ、手にとって読んでみてくださいね!
あわせてどうぞ!
【傾聴力アップ】鎌田實さんが説く「良いコミュニケーション」に必要不可欠なものとは?

こんにちは。どいつよしです。
『がんばらない』や『あきらめない』といった、読む人を癒やし、元気づける著書を多数世に送り出して来られたスーパードクターとして有名です。
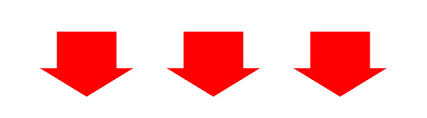
聴くことで患者さんの人生が変わる!?
鎌田さんは、終末期の患者さんに接する時、その人自身の人生を語ってもらうんだそうです。普段の生活の中でも使える!
鎌田さんのお話しは、医師と患者という関係で行われる「ライフビュー」というワークを例えにされていました。しっかり聴いて受け止めるには!?
聴き役のプロとしても心に留めておきたい言葉
人は語ることで癒やされます。だからこそ、しっかり耳を傾けてくれる「聴き役」の存在が重要です。
という言葉。
経験 に基づく語りを促す座り方
鎌田さんが実践されている、話し手の隣に横並びで座る。聴き役も話を聴いてもらおう!
おわりに
「人は語ることで癒やされる。そうなるためにはしっかり話に耳を傾けてくれる聴き役の存在が重要。」
書籍紹介
鎌田實さんはほんとにたくさんの本を出版されています。その中から、僕が読んで元気をもらったものを紹介します。
どの本もとても読みやすく書かれていますので、読書が苦手な方でも読み進めることができると思いますよ!
やさしい表現で書かれる鎌田さんの文章を読み進めていくと、心がじんわりと元気になっていくことがわかります。
ぜひ、手にとってみてくださいね!
あわせてどうぞ!
【傾聴力アップ】心理カウンセラーの「無条件の肯定的な眼差し(受容)」について理解し、実践していくには!?

ありの〜ままの〜♪
すがたみせるのよ〜♪
ありの〜ままの〜♪
じぶんに〜なるの〜♪
こんにちは。どいつよしです。
いきなり、映画『アナと雪の女王』の日本版主題歌『Let It Go 〜ありのままで〜』のサビからスタートしてみました。
今日のブログのテーマは、心理カウンセラーに必要な【無条件の肯定的な眼差し(受容)】です。
そう、クライエントが「ありのままの姿を見せて良いんだ」「ありのままの自分で良いんだ」と思うことができるようになるカウンセラーの態度で、心理療法の成功と関連があると言われる[ロジャーズの3条件]のひとつです。
ちなみに前回は、[ロジャーズの3条件]から心理カウンセラーの【自己一致】について書きました。
今回も、 H28年1月に参加した、『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本』という本を出されていて、ロジャーズの理論についても詳しい、関西大学大学院教授の池見陽先生の講座で学んできたことと、池見先生の著書から学んだことを織り交ぜて書いていきます。
また、[ロジャーズの3条件]は「受容、共感、自己一致」という訳され方が広く知られていますが、池見先生は【受容】という訳され方が好きではないそうで、【無条件の肯定的な眼差し】と表現されています。ですので、この記事でも、池見先生の表現を使って書いていきます。
なぜ【受容】ではなく、【無条件の肯定的な眼差し】なのか?
池見先生は、『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本』の中で、子育てを例えにして、【受容】ではなく【無条件の肯定的な眼差し】という表現を使っておられることを説明されています。
ようやく歩き始めた子どもがヨチヨチ歩いている。このくらいの子どもは、少し歩いては転んだり、尻もちをついたり。
そんな子どもの姿を親は「無条件」かつ「肯定的」な「眼差し」で見ている。
これは、子どもがヨチヨチ歩きを試みていることを「認める」ことでもある。
「ヨチヨチ歩きを受容する」となると、少しニュアンスが違っているように思われる。
確かに、「受容」という言葉は「受け入れて取り込むこと」という意味であることも考えると、ニュアンスが違いますよね。
また、『僕のフォーカシング=カウンセリング:ひとときの生を言い表す』では、
漢字の「受」は重たいイメージを伴う。わけがわからない攻撃的な人を前にして、「こんなに攻撃的な人もいるんだな」と「認める」ことはできても、カウンセラーがこの人を「受容」しなければならないと思うと、それはとてもたいへんなことだ。
と述べられています。
他にも、ロジャーズの原文【acceptance or unconditional positive regard】 の、【acceptance】は普通に訳すと「認める」となるはずで、「受容」という訳し方には疑問を感じるということも言われています。
以上のような理由から、池見先生は、【受容】という言葉ではなく、【肯定的な眼差し】という言葉を使われているのです。
無条件の肯定的な眼差しとは「認める」こと
池見先生によると、ロジャーズが伝えたかったカウンセラーの姿勢や態度としての無条件の肯定的な眼差しとは、
カウンセラーがクライエントを、無条件の肯定的な眼差しで見る、というか、認める。
ということ。
「あいてがどんな気持ちや考えを持っていても、それもその人らしさである。」と、その人のありのままを認めることが重要なのだそうです。
『アナと雪の女王』で例えると、どんなものでも凍らせてしまうことができる力を持った女性(エルサ)を眼の前にして、「どんなものでも凍らせてしまう力を持った人もいるんだな」と認めるということになりますでしょうか。
なぜ「認める」ことが必要なのか?
なぜ「無条件の肯定期な眼差し、というか、認めること」が心理カウンセラーに求められるのか。
池見先生の『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本』を参考に書いていきますね。
条件的な人間関係から自己概念は作られる
まず、知っておきたいこと。
僕たちは、これまでの人生の中で出会った、親、兄弟、友人、先輩、上司などとの人間関係のあり方を通じて、「自分」というものを形作ってきているけれど、そういった人間関係のほとんどは、「条件的である」ということ。
例えば、小さい頃から、親や身近な大人から「お前は明るくて良い子だね」と言われて育てられた人は、実は、「明るい」という条件を満たす限り「良い子」だと褒められる、という暗黙の条件を課せられて育ってきています。
この暗黙の条件をクリアしながら育っていくなかで「自分は明るい」と思うようになります。
このような、自分で自分を捉えたときのイメージのことを「自己概念 byロジャーズ」と表現します。
条件的な人間関係のもとで「明るい自分」は形作られ、自分で自分を捉えたときのイメージ(自己概念)も「明るい自分」だと認識していくというわけです。
※さらに、「明るい自分」という自己概念が、「もっと明るい自分」を形作っていく。そうすると、「もっと明るい自分」へと自己概念が強くなる・・・というように強化のスパイラルになって続いていきます。
自己概念に伴う価値条件が素直に感じることを妨げる
次に知っておきたいこと。
自己概念は同時に「自分はこんな人でないと生きている価値がない」といった価値条件を伴うということ。
だから、「自分は明るい」と思っている人にとって、〈暗い〉〈悲しい〉〈泣きたい〉というような「明るくない」感じは、「自分は明るくしてないと生きている価値がない」という自分の存在を否定するものであり、感じてはいけないものになってしまいます。
そこで、どうするか。その人はそれを感じないようにしてしまったり、「最近、疲れが取れない。病気かもしれない」と、歪曲して別のものとすり替えて理解しようとしてしまうのです。
つまり、人は「自分はこんな人だ」という自己概念があるから、その概念に合わないものは「自分の存在が脅かされるもの」として、意識から締め出そうとするということです。
カウンセリングに訪れる人は、自己概念に合わないものを体験していて、それを認めることができず、意識から締め出しても締め出しても解消されることがなく、生きるのがとても辛くなっている人であると考えられます。
心理カウンセラーに求められる態度
このような人が良くなっていくには、今まで意識から締め出してきたものに対して、「あってもいいんだ」と気づくこと。
どんな気持ちであれ、それを自分のものとして認めることができるようになることが必要なのだそうです。
こうなっていくには、どんな気持ちであれ、それを無条件に認めてくれる相手が必要。
その人こそが心理カウンセラーということになります。
心理カウンセラーに「あなたが明るいときも、暗いときも、どちらにも関心がありますよ。」と、それがあなたらしさであると、無条件に認めてもらってはじめて、クライエントは「暗い感じがあっていいんだ」と気づくことができるということなんですね。
また、「無条件の肯定的な眼差し、というか、認める」ことは、安心して話ができる場を作ることにも役に立つと思います。
「あなたは何を言ってもいいし、どんなことを感じてもいいんですよ」という、安心な場があってこそ、クライエントは、普段の人間関係では言えないことや、感じてはいけないと思っていることが言えるのだと思います。
そんな安全安心の場と時間を提供できる、心理カウンセラーを目指したいですね。
実践していくには?
「無条件の肯定的な眼差し、というか、認めること」を実践していくにはどうすればいいのでしょうか。
眼の前の人の存在自体を認める
僕は、まず、眼の前の人の存在自体を認めることからはじめました。これは、赤ちゃんのお世話をする仕事をしていた経験が生きています。
生まれたばかりの赤ちゃんは、泣く、ミルク飲む、寝る、排泄する、が主な活動で、生産性のあることはできませんよね。
でも、そこにいるだけでオッケーなんです。泣いてもオッケー。ミルク飲んでもオッケー。すやすや寝てもオッケー。ウンチをしてもオッケー。
「今この瞬間、ただそこに存在している。それだけでオッケー。」という感覚です。この感覚を応用して、話を聴くようにすることで、「無条件に関心を向ける」「ありのままを認める」ということができるようになっていきました。
ジャッジしない
そして、もうひとつ、ジャッジしない。これは、[魔法の質問]のマツダミヒロさんから学んだことですが、「まずは相手の話を受け止め、否定しない」ということです。
「受け止める」というのは、否定も肯定もせずに、「この人はこういうふうに考えているんだ」と、事実としてとらえること。
話を受け止めてあげることにより、「私はあなたの話しをちゃんと聴いていますよ」という意思表示にもなります。
ジャッジしないことを意識することで、否定や肯定といった、評価のメガネを通さずに、話し手のありのままを認めることができるようになってきたと思います。
自分の気持ちを「あるよね〜」と認める
それから、自分が感じていることに、とりあえず「そんな感じもあるよね」と言ってみるようにしています。いろいろ考えずに、まずは「あるよね」と言ってみる。
こうすることで、自分が感じているいろんな気持ちを、「ある」と認めることができるようになってきて、それが、話し手のありのままの姿を「認める」ことにも良い影響を与えているように感じます。
結論に至る思考の過程を充実させる
池見先生によると、「無条件の」という態度が維持できないことがあるのは、聴き手の一般的な理解から生じる感情や「思いやり」が、無条件になるのを難しくさせるからなのだそうです。
そして、重要なのは結論ではなく、結論に至る思考の過程を充実させることだということを、聴き手として認識しておくと楽になると述べられています。
思考の過程を充実させることの効果としては、
思考の過程を充実させることにより、その思考の過程が充実したもので、本人が深く自分を見つめ、そこにある様々な実感を注意深く吟味したうえで結論に至ったなら、
それがどのような結論であれ、それは本人にとっては本来的でよい結論であると言えるだろうし、また、周りのほとんどの人は、その過程から生じた結論には賛成するだろう
とのことです。
思考の過程を充実させるには、「存在自体を認めること」や「ジャッジしない」という態度を維持しつつ、繰り返しや要約を使いながら、話をじっくり聴いていくことが大切だなと思いました。
おわりに
いかがでしたか?今回は、ロジャーズの3条件の中から、「無条件の肯定的な眼差し(受容)」について、書きました。
ロジャーズの三条件の中で、一番理解していると思っていた「無条件の肯定的な眼差し(受容)」でしたが、池見先生の講座と書籍から学んでみると、
そもそも、なんで心理カウンセラーには、無条件の肯定的な眼差しが必要なのか?ということから理解をすることができました。
また、産業カウンセラー養成講座で学んだことをさらに深めて実践していくヒントも得られたので、本当に良かったです。
クライエントのありのままの姿を「認める」ことを、これからも実践し続けていくことで、クライエントが、
これでいいの〜♪
自分を好きになって〜♪
これでいいの〜♪
自分を信じて〜♪
ひ〜か〜り〜♪
あびな〜が〜ら〜♪
あるき〜だそう〜♪
と変化していけるような、お手伝いができればいいなと思います。
池見先生の講座はこちらでチェック!
池見先生の公式ホームページです。最新の開催講座が随時UPされています。ぜひ一度、池見先生のお話を生で体験してみてくださいね!
引用・参考文献
今回のブログで参考にしている池見先生の著書です。3冊を紹介します。
『心のメッセ-ジを聴く 』は、ロジャーズの3条件を「カウンセリング・マインド」という表現で説明していて、普段の生活レベルへの活かし方も書かれています。
ロジャーズの来談者中心療法についても、3条件をはじめ、たくさん書かれていますし、3条件の実践方法も書かれていて、すぐに実践へ移行しやすいものになっています。
一方で、『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本』はロジャーズの理論についての誤解を解く内容が書かれていたり、来談者中心療法以外の療法についても、池見先生が解説をされています。
そして、その上で、来談者中心療法のアップデート版ともいえる、フォーカシング指向心理療法について、事例を交えて書かれています。
ロジャーズをきちんと理解した上で、ジェンドリンを知ることができる、一石二鳥以上のお得な本でもあります。

傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本
- 作者: 池見陽
- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版
- 発売日: 2016/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
『僕のフォーカシング=カウンセリング:ひとときの生を言い表す』は、池見先生のフォーカシング指向心理療法について、日本のある場所で行ったフォーカシングワークショップでの出来事が書かれてあります。
体験ワークごとに、池見先生による詳しい解説があり、池見先生のフォーカシングはこういうものなんだ、という理解がすすむ本です。
先に挙げた2冊と比べて、ロジャーズについての記載は少ないですが、表現方法はいちばんやさしいのではないかと思います。
ぜひ、手にとって読んでみてくださいね!
合わせてどうぞ!
【傾聴力アップ】心理カウンセラーの「自己一致」について理解し、実践していくには!?

こんにちは。どいつよしです。
H28年1月に、『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本』という本を出されていて、ロジャーズの理論についても詳しい、関西大学大学院教授の池見陽先生の講座に参加してきました。
前回は、この講座で、[ロジャーズの3条件の「受容・共感・自己一致」が姿勢や態度のことである]、ということを学んだことを書きました。
今回は、そこから一歩進んで、心理カウンセラーとして知っておきたい、ロジャーズの3条件のうちの「自己一致」について、学んできたことを書きますね。
実践していくヒントもお伝えしますので、最後まで読んで頂けると嬉しいです。
自己一致と不一致とは?
そもそも、自己一致している状態とは、わかりやすく言うとどんなことを言うのでしょうか。池見先生の著書『心のメッセージを聴く 』を参考に、調べてみました。
ロジャーズは、下にあるようなベン図を用いて説明しています。

青の円を自己概念。緑の円を実感(悲しい、寂しい、嬉しいなど特定の内容をもった感情よりも複雑で漠然とした、実際に感じられる体験)とします。
自己概念とは、「自分はこういう人間だ」というような自分の定義や自己像のこと。
子どもの頃からの、両親や教師や友人といった[重要な他者]との関係によって形作られると考えられています。
「私は外向的だ」「私は子どもが好きだ」「私は泣かない」「私は辛抱強い」など、例えを挙げようとすると枚挙にいとまがありません。
自己概念がいったんできあがると、人はその概念に一致する生き方をしようとします。
また、できあがってしまった概念は変化しにくい性質を持っているので、固定化しやすいのだそうです。
例えば、僕が「私は外向的だ」という自己概念を持っていたとすると、「僕は外向的な人間だ。」と固定して捉えるようになります。
そうなると、僕の生き方や体験の仕方は、「私は外向的だ」という自己概念によって拘束されるようになっていきます。
そして、気付かないうちに、「私は外向的であらねばならない」とか「私は外向的であるべきだ」という強い意味を持つようになってしまいます。
でも、諸行無常という言葉があるように、心の実感は日々刻々と、今この瞬間も変化してゆくもの。
いくら「私は外向的だ」と思っている人でも、実際の体験として、誰にも会いたくないときはあります。
ここで生じる、「私は外向的であらねばならない」という固定化された自己概念と、「誰にも会いたくない」のような、日々刻々と変化する心の実感とのギャップが【不一致】ということになります。
さらに、【不一致】の状態である時は、実感されていることの多くは自己概念には素直に認識されず、否定されたり歪曲されてしまうのだそうです。
逆に、自己概念と実感の2つの円が完全に重なりあい、今この瞬間の変化の中における心の実感が全て自己概念に受け入れられ、統合される状態が理想的な自己一致なのだそうです。
クライエントは不一致の状態でやってくる
ロジャーズは、自己概念と実感の【不一致】が悩みや不適応、神経症、問題行動などといった心理的な困難の一つの要因であると考えたのでした。
カウンセリングに来られる人は、その人の自己概念と実感していることの間で、何かしらの【不一致】を抱えていらっしゃるということになります。
そして、カウンセリングを通じて、気付きや学びを得て、成長や変化をしていく過程で、【一致の状態】へと戻っていくことになるってことですね。
先ほどの例えにあてはめると、「僕には外向的な面も、内向的な面もあって、誰にも会いたくない時もある」という柔軟な自己概念になり、実感していることとの重なりが大きくなっていくということになります。
なぜカウンセラーが自己一致している必要があるのか?
カウンセラーが自己一致していることが必要であることについて、池見先生の著書『心のメッセージを聴く 』には以下の3点が記載されています。
・カウンセラーの自己一致が模範となって、クライエント自身が素直に「体験」を探索し、表現することを促進する。
・クライエントが気づいていないことをカウンセラーが感じ取り、それを表現することによって、クライエント自身の気付きが促進される。
・素直に感じるところでのクライエントとカウンセラーのやりとりは、治療的な関係を築き上げる基盤となる。
カウンセラーが【一致の状態】であることが、クライエントに良い影響を与えることになるということがわかります。
また、カウンセラーが気を付けなければいけないことは、「カウンセラーらしく振る舞わなければならない」という自己概念を持ってしまわないこと。
それは、「カウンセラーらしく振る舞わなければならない」となってしまうと、たちまち、感じていることや体験していることとの【不一致】に陥ってしまうから。
そして、「一致の達人」になろうと思う必要もないこと。
人生の中で常時「一致」している必要はないし、常にそのような感受性をもって生きることは、よほどの人でなければ不可能だからだそうです。
大切なのは、カウンセリングの時間の中では【一致】している必要があるということです。
カウンセラーは一人の人間として誠実であれ
池見先生によると、ロジャーズが伝えたかったカウンセラーの姿勢や態度としての自己一致は、
カウンセラーが自己一致している、というか、誠実である。
ということ。
カウンセリングの時間の中で、「カウンセラーらしく振る舞おう」とするのではなく、その瞬間瞬間で一人の人間として誠実であることが第一条件なのだそうです。
それは、クライエントが誠実に自分の気持ちと向き合おうとしている時に、カウンセラーが「カウンセラーという役割を演じる」もしくは「カウンセラーのふりをしている」ということであると、かえって足をひっぱることになるから。
カウンセラーが自分自身を偽っているので、クライエントの模範となることができず、クライエント自身が素直に「体験」を探索し、表現することができなくなってしまいます。
そうではなく、一人の人間として「私はあなたの話しを聴いていて、私も悲しくなってきました」と、自分の感じていることを素直に見つめ、それを表現でき、誠実に発言する。
また、素直に自分の理解を自由に話すことができる。
こういうカウンセラーの態度があってこそ、クライエントも自身の悲しさと向き合うことができるし、人間的な繋がりが感じられるのだそうです。
ちなみに、池見先生も「クライエントの話しが退屈過ぎて眠気に襲われながらも、カウンセラーとしての役割で話を聴き続けた」という、「カウンセラーが誠実でない」ご経験をされています。
このお話しは、池見先生の著書『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本』に詳しく掲載されてありますので、ぜひ、読んでみて頂きたいです。
僕も、この池見先生のエピソードが好きで、折に触れて読み返すようにしています。
どう実践していくか?
「自己一致、というか、誠実である」ことを、実践していくにあたって、まずは、「カウンセラーらしく振る舞おう」とならないように気をつけることが大事かと思います。
でも、頭ではわかっていても、クライエントから「先生お願いします。」と言われると、知らず知らずのうちに、「カウンセラーらしく振る舞おう」となってしまいそうです。
そこで、行動から入っていくのが良いのではないかと考えます。
クライエントの話を聴いて、自分がどんなことを感じたのか、クライエントに伝えてみる。それが難しいなら、書いてみる。
クライエントの話しを要約する時に、「自分はこのように理解しましたが合っていますか?」という意味で要約をする。
最初は、「カウンセラーらしく振る舞おう」というのがあったとしても、行動を続けていくうちに、それが薄れていって、いつの間にか「偽りのない、一人の人間として」クライエントの話に耳を傾けることができるようになっていくのではないでしょうか。
また、普段から折に触れて自己概念をチェックすることも良いのではないかと。
「一致の達人」になる必要はないということでしたが、自分が感じたことや体験したことについて、「私らしくない」というような認められない気持ちが湧き上がってきたら、
「私は〇〇である」という自己概念が、狭くなり過ぎてはいないか、強くなり過ぎてはいないか確認して、「私は〇〇もあるし、〇〇もある」というような、柔らかな自己概念になるように軌道修正をしていくということですね。
おわりに
いかがでしたか?今日は、池見先生の講座で学んだことから、心理カウンセラーとして知っておきたい「自己一致」について書きました。
池見先生の講座に参加することで、カウンセラーが自己一致しているというのはどういうことなのか、理解することができました。
また、こうやってブログに書いていく中で、そもそも自己一致と不一致ってなんなのか?というところについても理解が進みました。
池見先生から「自己一致」について学んだことの中から、僕は、“クライアントとの関係において、「カウンセラーという役割を演じる」もしくは、「カウンセラーのふりをしている」のではなく、瞬間瞬間において「偽りのない」素直な人間として、存在していること。”ということを、まずは大切にしていきたい思います。
池見先生の講座はこちらでチェック!
池見先生の公式ホームページです。最新の開催講座が随時UPされています。ぜひ一度、池見先生のお話を生で体験してみてくださいね!
引用・参考文献
今回のブログで紹介している池見先生の著書です。2冊を紹介します。
『心のメッセージを聴く』は、中核3条件を「カウンセリング・マインド」という表現で説明していて、普段の生活レベルへの活かし方も書かれています。ロジャーズの来談者中心療法についてもたくさん書かれています。
一方で、『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング』はロジャーズの理論についての誤解を解く内容が書かれていたり、来談者中心療法以外の療法についても、池見先生が解説をされています。
そして、その上で、来談者中心療法のアップデート版ともいえる、フォーカシング指向心理療法について、事例を交えて書かれています。
ロジャーズをきちんと理解した上で、ジェンドリンを知ることができる、一石二鳥以上のお得な本でもあります。

傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング―感じる・話す・聴くの基本
- 作者: 池見陽
- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版
- 発売日: 2016/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
ぜひ、手にとって読んでみてくださいね!
あわせてどうぞ!
良好なコミュニケーションを取るために心に留めておくと良い名言

対人関係において言葉を使ってのコミュニケーションは欠かせません。でも、言葉というものはしばしば使い方に苦労するものでもあります。
言葉は時には相手を幸せにし、時には相手を傷つけてしまう。使い方によって、暖かく包み込む毛布にもなれば、鋭く切り込む刃物にもなります。
メールやLINEを使った、相手の表情が見えない言葉のやりとりでは、何気なく送信した言葉が、意図しない受け取り方をされて、大きなトラブルに発展することもしばしば。
SNSが発達した現代においては、誰もが自分の意見を発信できる反面、誤った言葉を使ったことによって、またたく間に炎上してしまうことも珍しいことではありません。
こんなはずじゃなかったのに。。。と、後悔すること、僕もたびたび経験しています。
だから、僕を含めて誰もができることなら良好なコミュニケーションを取りたいと思っているのも事実です。巷に溢れているコミュニケーション本の多さがそれを物語っています。
本に書かれているメソッドを実践していくことができれば、コミュニケーションは以前より良好なものとなっていくでしょう。
でも、僕は、言葉を発するその人に言葉を受け取る側への配慮や気遣いがないとせっかくのメソッドも本領を発揮できないと思います。
言葉を発する側の心掛けを教えてくれる名言があります。
それは、
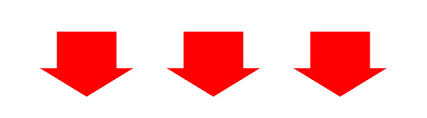
というものです。
この名言を残されたのは、昭和45年に大阪で開催された日本万国博覧会の有名なテーマソング「こんにちは~♪こんにちは~♪せかいの~♪くにから~♪」を歌っておられる三波春夫さん。
三波さんの芸に対する真摯さは人一倍だったとされ、
「いかに大衆の心を掴む努力をしなければいけないか、お客様をいかに喜ばせなければいけないかを考えていなくてはなりません。お金を払い、楽しみを求めて、ご入場なさるお客様に、その代償を持ち帰っていただかなければならない。」
と語ってもおられます。
三波春夫さんが仰った、
私の声が私の口から離れた瞬間、それはもう大衆のもの
という言葉は、
対人関係でのコミュニケーションにもあてはめていくことができます。
1対1の場合であれば、「私の声(言葉)が私の口から離れた瞬間、それはもう相手のもの」となりますし、
1対多の場合であれば、「私の声(言葉)が私の口から離れた瞬間、それはもうみんなのもの」となります。
ブログやSNSでの発信であれば、「私の声(言葉)がインターネットに流れた瞬間、それはもう世界中の人のもの」となります。
声(言葉)が私の口から出た時には、それはすでに私のものでは無くなっている。
その声(言葉)が届く人にどんな影響を与えることになるのかを想像して、発言していくようにしていければ、バッドコミュニケーションによるトラブルを防ぐこともできていくのではないでしょうか。
そしてそれは、口からの声や言葉に限らず、ブログやツイートなど、自らが発信するもの全てにもあてはまりますよね。
「発した瞬間から相手や大衆のものになる」ということを僕も心に留めて、ココロの皮むきブログを見てくれた人に少しでも良い影響を与えられるようにこれからも書き続けていこうと思います。
読者様は神様です!
あわせてどうぞ!